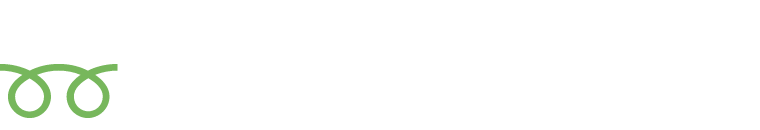NEWS&
COLUMN
ニュース・コラム

お役立ち情報
親亡き後 ~いつかその時のために~
2025.08.27
福祉・学校全般
皆様こんにちは。
ジェイアイシーセントラル福祉営業部の佐藤です。
今回は障害のある方の親御さんの多くが心配をしている『親亡き後』についてお話しいたします。
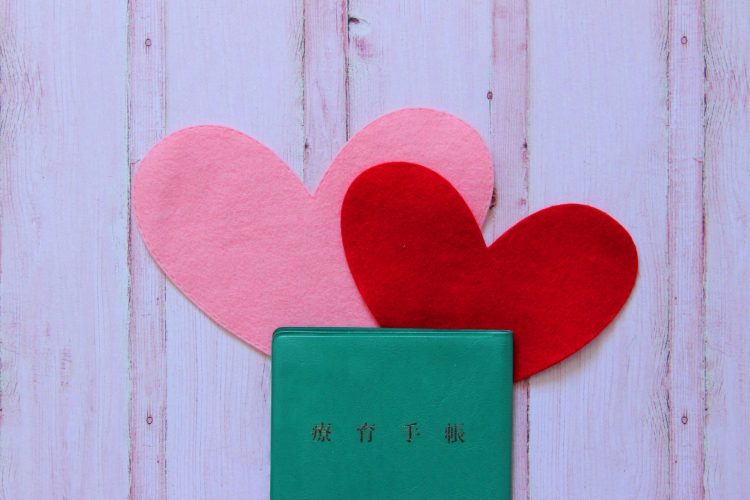
さて、毎回好評をいただいております『JICCセミナー』ですが、先日7月中旬に記念すべき20回目が開催されました。
今回のお題は、『成年後見制度をわかりやすく学ぶ~いつかその時のために、親として知っておきたいこと~』。
講師には、今池法律事務所弁護士山下先生と社会福祉連携推進法人となりの藤山先生のお二人をお招きしました。
リンク:https://www.jiccentral.co.jp/news-column/p3570/
法律のプロと福祉現場のプロでいらっしゃるお二人からは、制度の基本から具体的な事例まで解説とご紹介をいただきました。
セミナー終了後、参加者様からは『成人後見制度セミナーは色々な場所で聞いてきましたが今日のセミナーが1番わかりやすかったです。』などの嬉しいご感想も。
ご参加いただいた多くの皆様、講師の御二方、本当にありがとうございました。
※JICCセミナーチームのみんなもお疲れ様でした。
今回お話をお聞きして、
『成年後見制度は、親亡き後への備えの大切な仕組み、一つの手段であり、本人・家族の状況を踏まえて必要な時期が来た時に活用をするべきです。ただ、成年後見制度は万全ではなく、親の代わりはできません。』
という講師の方からの一言に、親亡き後への準備の難しさを感じさせられました。
親亡き後を考えるうえで障害のある方の親子の状況・実態を見てみましょう。
令和4年度に厚生労働省が実施した『障害者手帳所持者等の生活実態等の状況について』の調査に協力した療育手帳所持者1,831名のうち、81.5%が主な支援者が『親』と回答しており、いまだ障害のある方の“両親への依存度の高さ”がうかがえます。
出典:「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の結果について
それでは『親亡き後への準備』についてポイントを見ていきましょう。

親なき後への準備① 生活費など経済的、金銭面への備え
障害のある方の将来の生活スタイルを想像して受給できる手当や年金の額など収入について考えましょう。
逆にどれくらい生活費がかかるのか、出費が想定されるのか知っておく必要があります。
そのうえで、ご家族のライフプランを念頭にご両親が何歳まで働けるのか?経済的なバックアップと資産形成など準備が出来る期間は何時までか?などなど、多岐にわたる検討・準備が必要になります。
親なき後への準備② お金の残し方、管理の仕方など
せっかく親御さんが一生懸命蓄えた大切な資産を、どのように残し、渡し、使ってもらうか。
成年後見制度をはじめ信託制度や遺言など、それぞれのご家庭の状況に応じた各種制度を選択し、場合によっては組み合わせて活用する必要があります。
最近は障害福祉に詳しい専門家の方々も大勢いらっしゃいます。
まずは相談できる窓口を探すところから始めてみてはいかがでしょうか。
親なき後への準備③ 生活基盤の準備
『生活をする場所の確保』『福祉サービスをはじめとする支援体制の確保』などの親亡き後の受け入れ施設は絶対的に不足しており、就労や日中の居場所を含めて当事者が長く安心して暮らせる環境、基盤の準備、確保がもっとも重要だと考えられます。
日頃利用している障害福祉サービス事業者の方が、もっとも身近な相談者かもしれません。
その時はいつか突然やってくる
『まだ早い、またいつか…』とお考えの親御さんも大変多くいらっしゃいます。
しかし“その時”は、いつか突然やってきます。
これまでも多くの先輩方や先生方が口を揃えておっしゃっていたことは、『早い段階から少しずつ、計画的に準備をする。』ということです。
先にあげましたポイントを参考に、今日から公的支援の勉強と私的準備を始めましょう!

このような皆様のご不安事に、ジェイアイシーセントラルでは『未来のあかり事業』にて親亡き後への相談を受け付けしております。
リンク:https://www.jiccentral.co.jp/miraino-akari/ から、お気軽にお問い合わせください。
※なお愛知県にご在住のお客様のみへのサービスとなりますことをご了承下さい。
私たちJICセントラルは、これからも自らを磨きながら『親亡き後』へのご支援ができればと思っております。
執筆者プロフィール
福祉営業部 さとう たつや
福祉関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。